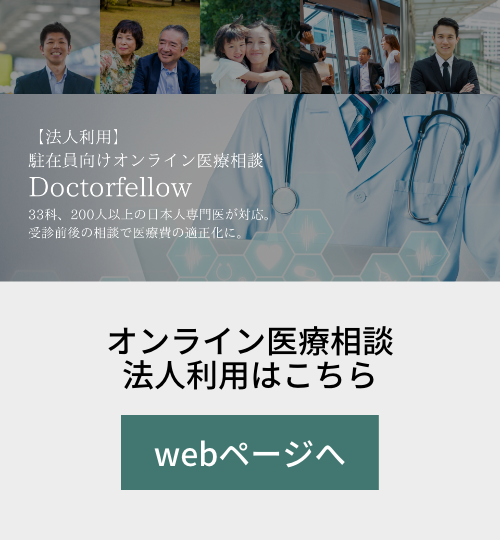アメリカ渡航・駐在時に推奨されるワクチン(予防接種)

※本記事の最終更新日 2023年5月
アメリカへの赴任・渡航時に検討が推奨されるワクチン・予防接種、駐在中に気を付けたい感染症・病気についてまとめております。
※他のWebサイト等の情報を参照、一般的な情報提供としての掲載です。
Contents
■アメリカで気をつけたい感染症・病気は?
アメリカで気を付けたい感染症・病気としては、ライム病、デング熱、狂犬病、ノロウイルスなどが挙げられます。詳しくは、厚生労働省「アメリカ 気候と気をつけたい病気、受けておきたい予防接種、持っていきたい薬」や外務省webページ世界の医療事情アメリカ合衆国ニューヨーク・世界の医療事情アメリカ合衆国ワシントンDC周辺などをご確認下さい。
■(成人)アメリカ入国の際に必要/推奨されるワクチン
アメリカ入国に際して必要とされるワクチンはありません。
しかし、可能であればA型肝炎ワクチン、破傷風ワクチンを接種しておくことが勧められています。
(1)A型肝炎とは?
A型肝炎はA型肝炎ウイルスによる一過性の感染症です。
- 感染経路
糞便から排泄されたウイルスが人の手を介して、水や氷、野菜や果物、魚介類を経て口に入ることで感染します。過去には、貝類による集団感染もありました。性交渉時に感染することもあります。
- 症状
ウイルスに感染し、2~7週間の潜伏期間の後に、急な発熱、全身のだるさ、食欲不振、吐き気や嘔吐が見られ、数日後には黄疸(皮膚や目の白い部分が黄色くなること)が現れます。
成人は小児よりも所見や症状が現れやすく、高齢者では重症度と死亡率が高くなります。ただし、日本では60歳以上の人の多くが免疫抗体を持っています。
感染した場合には、症状の発現前と症状の消失後にも、数週間はウイルスを排泄しますので、他人に感染させないように注意しましょう。
- 予防接種について
日本では、ワクチンは2~4週間の間隔で2回接種します。約半年後に3回目の接種をすると免疫が強化され、5年間は有効といわれています。国と製剤によって接種方法が異なるため、アメリカ現地医師の指示に従ってください。
(2)破傷風とは?
破傷風は、破傷風菌がうつることによってかかり、口や手足のしびれがおこる病気です。治療が遅れると死亡することがあります。
- 感染経路
けがをしたときに傷口から破傷風菌が体の中に入ります。破傷風菌は、世界中の土のなかに存在します。特に、動物の糞便で汚染された土壌が危険です。
- 症状
感染して3日から3週間からの症状のない期間があった後、口を開けにくい、首筋が張る、体が痛いなどの症状があらわれます。その後、体のしびれや痛みが体全体に広がり、全身を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れたのちに死亡します。
- 予防接種について
正しい方法で接種を行うと免疫が10年間持続します。旅行中にケガをしたときにも破傷風ワクチンが必要になることがありますので、早めに医師に相談して下さい。
(参照:外務省 世界の医療事情 アメリカ ロサンゼルス周辺、厚生労働省検疫所 気候と気をつけたい病気 アメリカ、 A型肝炎、破傷風)
■(子ども)アメリカ滞在、入学の際に必要なワクチン、定期予防接種
できるだけ日本で定められた定期予防接種を受けておき、アメリカに到着後は、現地のワクチン接種計画に従って、予防接種を行うことが大切です。
また、アメリカ現地校に入学・入園する際にはワクチン接種証明の提出を求められます。日本とアメリカでは、必要なワクチンの種類及び接種回数が異なるので注意が必要です。州によっても少しずつ異なる事がありますので、必ず入学する州の規程がどうなっているかを確認してください。
・アメリカの小児定期予防接種一覧(ワシントンDC周辺)
| 予防接種 | 初回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
| B型肝炎 | 出生時 | 1~2カ月 | 6~18カ月 | ||
| ロタウィルス | 2カ月 | 4カ月 | 6カ月 | ||
| 3種混合(DTaP) | 2カ月 | 4カ月 | 6カ月 | 15~18カ月 | 4~6歳 |
| インフルエンザ菌b型(Hib) | 2カ月 | 4カ月 | 6カ月 | 12~15カ月 | |
| 肺炎球菌(PCV) | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6ヵ月 | 12~15ヵ月 | |
| ポリオ(IPV) | 2ヵ月 | 4ヵ月 | 6~18ヵ月 | 4~6歳 | |
| インフルエンザ | 6か月以降毎年接種。8歳以下で最初の接種時には、4週間以上の間隔で2回接種。 | ||||
| MMR(麻疹、流行性耳下腺炎、風疹) | 12~15ヵ月 | 4~6歳 | |||
| 水痘(Varicella) | 12~15ヵ月 | 4~6歳 | |||
| A型肝炎 | 12~23ヵ月 | 1回目から少なくとも6か月をあけて。 | |||
(2)7~18歳に奨励されているワクチン接種スケジュール
| 三種混合(Tdap) | 11歳~12歳で1回接種。 |
| ヒトパピロマウイルス(HPV) | 11歳~12歳で2回接種。15歳以上は3回。(1回目から1~2か月後に2回目、その6か月後に3回目)9歳からでも接種可能。9歳~14歳は2回。(1回目から6~12か月後に2回目) |
| 髄膜炎菌(MCV4) | 11歳~12歳で1回。16歳時にブースター。 |
■アメリカで感染症・病気になったら
アメリカの日本語対応可能な病院・クリニックは、こちらよりご確認ください。
アメリカの医療費についてはこちらの記事をご参照ください。
その他の注目記事のまとめはこちら
※【株式会社Medifellow注目記事まとめ】過去の注目記事はこちらをご覧ください。※

弊社は33科500人以上の専門医の体制で、海外展開企業(主に海外駐在員)向けのオンライン診療・医療相談サービスを運営、厚労省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準拠、「オンライン受診勧奨」サービスを提供、必要に応じて、現地病院受診時の紹介状作成等も行っております。また、厚労省の実施する「オンライン診療研修」を修了の専門医が対応に当たっています。病院の受診前後に活用、不安解消はもとより、医療の内容や医療費適正化、生産性向上に寄与します。健康経営、福利厚生、感染症BCPの対策に導入をご検討下さい。
編集者プロフィール

- 「一人ひとりの心と役割が輝く社会を創る」ことをミッションに、マーケティング、カスタマーサクセス(コミュニティ)、PRの一貫したコミュニケーション作りを担う。大阪教育大学卒業。卒業後は教育事業会社で広報・採用を行い、その後飲食店向けFinTech&SaaS企業にてProductPR、カスタマーサクセス、コミュニティ運営を担当。同時に、日本の誇れる医療と安心を世界中に届けるビジョンに共感し、広報担当として株式会社Medifellowに参画。広報、マーケティング、グラフィックデザインを行っている。