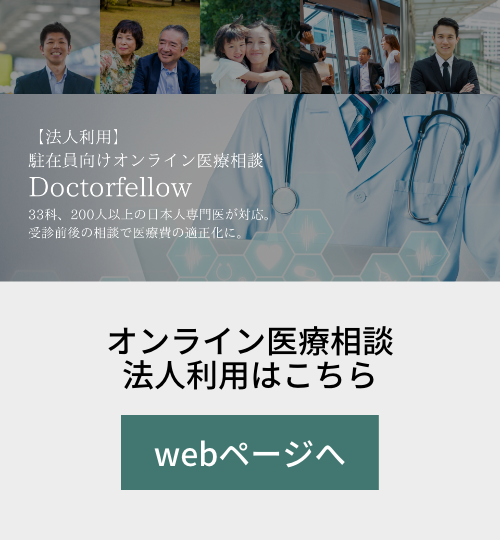セカンドオピニオンの費用、やり方、有用性について

本記事では、セカンドオピニオンの費用、やり方、有用性についてまとめています。
”「高い専門性と豊富な経験を持つ専門医」が行う医療相談こそが本質的な「セカンドオピニオン」であり、正しく活用すれば有用性がとても高い”ということが結論です。
Contents
セカンドオピニオンとは何か?
患者が検査や治療を受けるに当たって主治医以外の医師に求めた「意見」、または、「意見を求める行為」。主治医に「すべてを任せる」という従来の医師患者関係を脱して、複数の専門家の意見を聞くことで、より適した治療法を患者自身が選択していくべきと言う考え方に沿ったものである。
Wikipedia「セカンドオピニオン」
医療で使う場合、セカンドオピニオンとは、主治医が診断した病名やその後の治療方針に不安だった時に、適切な治療方針の選択に繋げるために、主治医以外の医師に意見を求めることを指しています。弊社でも、国内はもとより、海外在住日本人(駐在員等)や海外の中国人、ベトナム人等の日本人以外の方からもオンラインセカンドオピニオンの依頼を日々受けております。
ー医療のプロである医師が診断や治療方針を誤るの??ー
医師も全知全能の神ではありません。患者さんの診察や治療でとても忙しくしていたり、また、専門分野も細分化されており、少しでもその専門分野からずれた内容になってくると力不足になってしまう可能性もあります。そのような時に、その専門分野のスペシャリスト、「医師が選ぶ医師」が行うことで始めて有用性があるのがセカンドオピニオンです。
セカンドオピニオンに関する論文(海外)
海外ではセカンドオピニオンの介入により、診断した病名の見直しや医療費の縮減に繋がったとする論文が数々出されております。
セカンドオピニオンの海外での市場規模は大きく約3,300億円(2019年)あり、2027年には約1.1兆円規模までに拡大することが推計されています。
The medical second opinion market was valued at US$ 3, 204.57 million in 2019 and is projected to reach US$ 10, 739.48 million by 2027; it is expected to grow at a CAGR of 16.8% during 2020-2027.
Global Medical Second Opinion Market Forecast to 2027 – COVID-19 Impact and Analysis
セカンドオピニオンの状況(国内)
それでは国内のセカンドオピニオンの市場規模はどの程度なのでしょうか?中医協の資料中の診療情報提供料Ⅱ(セカンドオピニオンを受けるために、患者が主治医から必要な医療情報をもらった際に病院が算定できる診療報酬)の算定回数(出典︓社会医療診療⾏為別統計・調査(各年6月審査分))から想像すると国内のセカンドオピニオン市場規模は、数十億円程度でしょうか。
国内では主にはがんを対象にセカンドオピニオンが利用されておりますが、とあるアンケートによると調査対象のがん患者のうち3割程度しか利用していないと言う結果も出ております。がん患者でも利用されていない方が相応いることと、また、本来がん以外の病気でもセカンドオピニオンは利用できることを考えると、まだまだ国内での活用余地も大きいかと考えられます。
セカンドオピニオン利用なぜ進まない?
セカンドオピニオンの場合、患者から主治医にセカンドオピニオン用の診療情報提供書や検査情報等の作成を依頼しなければならず、主治医との信頼関係を気にしてセカンドオピニオンを踏みとどまってしまう患者も一定いるようです。主治医との信頼関係を気にして情報提供書等は取得せず(こっそりと)そのまま市中の病院・医師に受診しようとしても、現在の日本の医療制度においてはそのような病院受診はほぼ受け付けてもらうことはできません。特に、セカンドオピニオンを提供するような大きな病院では、必ず診療情報提供書(紹介状)を求められるからです。
しかし最近では、医師の間ではセカンドオピニオンを希望されることはあたりまえとなってきていますし、新医師臨床研修制度が施行(平成16年)されてからは医学教育でも一般的な仕組みとしてセカンドオピニオンは教育されていますので、主治医の先生から悪感情を抱かれることはまずないでしょう。心配せずに主治医の先生にセカンドオピニオンを希望する旨を申し出てはいかがでしょうか。
セカンドオピニオンの費用は?どんなところへ?やり方は?
セカンドオピニオンは自費診療になり、各々の病院が独自にセカンドオピニオン費用を定めています。普通に市中病院を保険診療で受診することはセカンドオピニオンではありません。せっかく別の先生の意見を聞くのですから、専門性の高く経験豊富な「医師から選ばれるような医師」に依頼してこそのセカンドオピニオンです。いわゆる地元の基幹病院と呼ばれるところや、全国的に有名な病院では、ほぼ必ずセカンドオピニオンの窓口について紹介しています。気になる病院や先生がいれば、セカンドオピニオンの窓口やセカンドオピニオンのやり方について、まず各病院のホームページを見てみてください。指定のやり方にそったセカンドオピニオンのための手続きは必要ですが、有用性あるセカンドオピニオンを受けることで、それまでなかった選択肢に気付くこともあるかもしれません。
弊社オンライン診療・医療相談サービスでのセカンドオピニオンもご検討ください
33科(全診療科)500人以上の専門医体制で、オンラインセカンドオピニオン等のオンライン診療・医療相談サービスを提供しています。全診療科のセカンドオピニオン、医療相談に対応、主には海外駐在員等、海外在住日本人の医療不安解消のサポート、また、医療の内容の適正化に繋げることで医療費適正化に寄与しています。弊社セカンドオピニオンサービスをご検討下さい。
編集者プロフィール

- 株式会社Medifellow
- 岐阜薬科大学薬学部卒、薬学士。医療機関の経営コンサルティングを経験。大学病院や自治体病院、公的病院の経営改善に従事。その後、HR業界で採用支援コンサルティングを経験。海外駐在員や日本人現地採用、外国人の転職などクロスボーダーの転職・就職支援に従事。